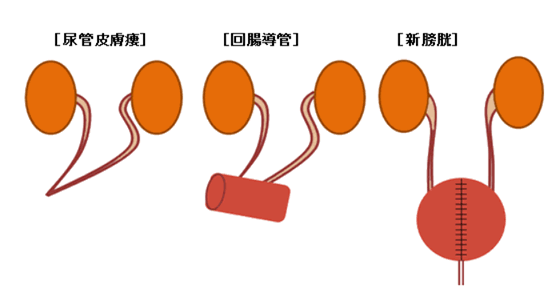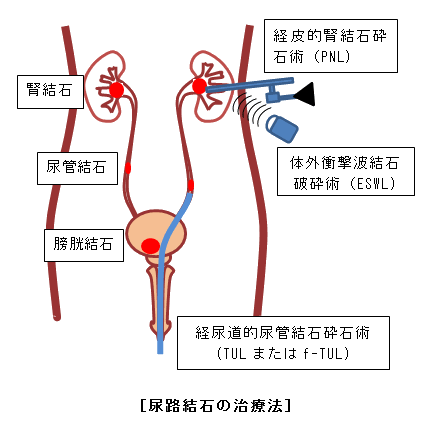腎癌(腎細胞癌)
症状・診断・治療方法
腎臓はそら豆の様な形をしており、背中に左右1対ある臓器です。主な働きは、血液を濾過して尿を作ります。その他、血圧を保つホルモンや、赤血球をつくるホルモンも作り出しています。 腎臓は尿を作る部分(腎実質)と尿が流れる部分(腎盂)とに分かれますが、腎細胞がんは、腎実質から発生するがんのことです。腎臓に画像検査などで腫瘍が認められた場合は大半が悪性(がん)であり、腎がんを念頭に置いた治療計画が必要になります。
原因・症状
腎がんは喫煙や肥満が原因とされています。約80%の腎がんは症状がなく、CTや超音波検査などの画像診断で偶然発見されます。このようながんを偶発がんと呼びますが、手術で完全に切除できれば比較的予後は良好です。一方、古典的三大症状(血尿、腹部腫瘤、側腹部痛)から発見される腎細胞がんは、非常に進行しており、転移を伴う進行がんであることが多く、予後も悪いとされています。
診断
ほとんどの腎がんが超音波検査、CT、MRIなどの画像で診断ができます(腎がんには腫瘍マーカーは存在しません)が、良性腫瘍との鑑別が難しいこともあります。画像での診断が困難な場合は生検(針で組織を採取して調べること)で診断をする場合があります。
治療方法
(1)手術療法
小さな癌であれば腎部分切除(がんの部分だけを切り取り、腎臓を温存する手術)の対象となりますが、大きながんでは、腎臓を全て摘出する必要があります。以前は開放手術が多かったですが、近年は腹腔鏡下手術を行うことが多いです。部分切除術は内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」による腹腔鏡手術を行う施設もあります。
(2)温存療法
手術だけではなく凍結療法やラジオ波凝固療法(アブレーション治療)を行う場合もあります。アブレーション治療とは、腫瘍に治療用針を直接差し入れて、熱したり急速に凍らしたりすることで治療する方法です。
(3)薬物療法
肺や骨に転移があって切除が難しい場合には、免疫チェックポイント阻害薬を用いた複合免疫療法や分子標的薬による薬物療法を行います。
前立腺癌
症状・診断・治療方法
前立腺は男性のみに存在する臓器で、膀胱のすぐ下で尿道を取り囲むかたちで存在しています。主な働きは精液の一部を産生し、射精における収縮や尿の排泄なども担っています。前立腺がんは加齢とともに発生頻度が増加し、その多くは60歳以降に認められます。前立腺がんは一般的には進行速度が遅いがんと考えられていますが、進行の早いものもあり、欧米では男性のがんの中で罹患率は最も高いものの一つです。日本でも近年罹患率、死亡率ともに増加しており、非常に身近な癌と考えられます。
原因・症状
前立腺がんが進行してくると、トイレが近い、尿の出が悪いなどの症状、また骨に転移しやすいため腰痛等を訴えることもありますが、初期にはほとんど症状はありません。そのため、大半は、検診等での前立腺特異抗原(PSA) の数字が高くなることで発見されています。
診断
PSAが4 ng/ml 以上であれば前立腺がんを疑います。その場合は超音波検査、直腸診、MRI検査などで前立腺の状態を確認しますが、がんの確定には針を刺して前立腺の祖組織を採取する生検によって確定します。生検でがんが確定すれば転移しているかをCT検査、骨シンチグラフィー検査などで調べます。
治療
前立腺がんの治療は手術療法、放射線療法、ホルモン療法の3つが中心になります。治療方針を決める際は年齢、がんの病期(どの程度進行しているか)、がんの悪性度(グリーソンスコア)、PSA値によって判断します。基本的に患者さんが若くて、がんが前立腺に限局している場合は手術療法や放射線療法を選択します。一方で転移がある場合はホルモン療法を選択します。また、PSA値が低く、悪性度が低い場合は積極的な治療を行わず経過観察を行うこともあります(PSA監視療法)。その場合は定期的なPSA検査が必要です。
(1)手術療法
従来は開腹手術を行っていましたが、近年は腹腔鏡手術やダヴィンチなどのロボットを用いたロボット支援腹腔鏡手術を行うことが多いです。手術で前立腺を摘出し膀胱と尿道をつなぎ合わせます。約2週間の入院が必要です。 術後合併症として腹圧性尿失禁がありますが、手術手技の発達により少なくなっています。
(2)放射線療法
放射線療法には主に外照射療法、小線源療法、重粒子線療法があります。
外照射療法は外部から前立腺に放射線を照射する治療です。約4週間の外来通院が必要です。最近は、コンピューターとCTスキャンを用いて、正確に前立腺に照射することが可能となっています。
小線源療法は小さな放射線源を前立腺に埋め込む放射線療法で数日間の入院が必要です。 外照射に比べ副作用は少なく、性機能が温存できる可能性が高いことが利点です。
重粒子線療法は炭素粒子を用いて前立腺に照射しがん細胞を治療します。
(3)ホルモン療法
前立腺癌は男性ホルモン(テストステロン)により増殖するため、このホルモンの働きを抑える治療法です。テストステロンの約95%を産生する精巣を摘出する方法(除睾術)と、LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)類似薬によって精巣からの男性ホルモン産生を低くする方法があります。 これらの去勢術に加えて、抗アンドロゲン剤を内服することにより、強力ながん増殖を抑制するのが一般的です。
(4)化学療法
ホルモン療法でも抑えきれなくなった前立腺がんに対して適応になります。近年はさまざまな薬物が開発されています。
腎盂・尿管癌
症状・診断・治療方法
腎盂・尿管は、腎臓で生成された尿の通り道であります。ここに腫瘍が発生した場合に腎盂尿管癌となります。また、腎実質に発生する腎癌と腎盂に発生する腎盂癌は、まったく別であり、治療法も大きく異なります。しかし、膀胱は腎盂、尿管と同じ尿路上皮という組織であるため、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌は同じ分類と考えられます。
症状
血尿で発見されることが多いですが、腫瘍による尿の通過が障害されると、腎臓が腫れ腰痛が出現することもあります。
診断
尿検査や超音波検査に加え、腹部レントゲン検査(CT、排泄性腎盂造影・逆行性腎盂造影等)にて尿管・腎盂の形状を精査します。これにても、診断がつかない場合は、麻酔下で内視鏡検査(尿管鏡検査)を行う必要があります。その他、癌の進行程度(病期)を調べる検査として、CT、MRIおよび骨シンチがあります。
治療
【手術】
転移がない場合は、腎尿管全摘除術を行います。腎尿管全摘除術には開腹手術の他に腹腔鏡、ロボット支援手術があります。腹腔鏡やロボット支援手術では小さな傷で手術ができますが、腎~尿管を一塊にして摘出する必要があるため、最終的に下腹部に切開(約7cm程度)が必要となります。また、手術前に白金製剤を用いた抗癌剤治療をしたり、再発リスクの高い場合は術後治療として抗癌剤治療や免疫チェックポイント阻害薬による免疫治療を追加することもあります。
【薬物治療】
診断時に転移のある場合や手術が困難な場合は、抗癌剤を用いた薬物治療を行います。また1次治療である抗癌剤治療後には2次治療として免疫チェックポイント阻害薬を用いた免疫治療、その後の再発には3次治療としてエンホルツマブ ベドチンという抗悪性腫瘍剤による治療を行います。
前立腺肥大症
症状・診断・治療方法
前立腺肥大症は男性高齢者における最も一般的な疾患の一つであり、それによって引き起こされる 下部尿路症状は患者さんのQuality of Life(生活の質)を著しく悪化させています。
前立腺が加齢とともに肥大していくと、尿道を圧迫してしまいます。当然、前立腺が尿道を圧迫すると出口が狭くなり尿が出にくくなります。(排尿困難)
一方、膀胱は何とか尿を出そうと頑張るため、膀胱の筋肉が発達し筋肉質になり、膀胱の壁が分厚くなってしまいます。そうすると、膀胱の本来ある伸びる力(柔軟性)が失われカチカチになり、少し尿がたまるとすぐに一杯になり我慢できず、尿を出そうとしてしまいます。これが頻尿や尿意切迫感として症状に現れます。
つまり前立腺肥大症の2大症状は①排尿困難 ②頻尿、尿意切迫感(過活動膀胱)であり、男性の過活動膀胱の最大の原因になります。
現在、前立腺肥大症による排尿障害に対する治療においては、様々な薬物療法および手術療法と選択肢は数多く存在しています。
治療
(1)内服治療
前立腺肥大症の薬物治療の要点は上記の2大症状を改善させることです。すなわち次の2つが要点になります。
1.前立腺により圧迫された尿道の抵抗を改善させる(排尿困難を改善)
2.膀胱の柔軟性を回復させる(過活動膀胱を改善)
治療としては、まず1.の尿道の抵抗を改善させることが最も重要です。尿道の抵抗を減らすだけで膀胱の柔軟性が回復し過活動膀胱も改善する場合があります。
前立腺肥大症に使用される薬剤は以下の5種類に分類されます。
1.前立腺により圧迫された尿道の抵抗を改善させる(排尿困難を改善)薬剤
①α1受容体遮断薬
②PDE5阻害薬
③5α還元酵素阻害薬
2.膀胱の柔軟性を回復させる(過活動膀胱を改善)薬剤
④β3受容体作動薬
⑤抗コリン薬
これらの薬剤を患者さん個々に合わせて組み合わせることにより治療を行っていきます。
(2)手術療法
上記の薬物療法で症状の改善が得られない場合や前立腺肥大症に伴う合併症(血尿、結石、尿閉)が生じた場合は手術療法を行います。最近様々な手術療法が開発されていますが、それぞれの術式には一長一短があり主治医と相談の上、最適な手術治療を選択する必要があります。
現在本邦で可能である前立腺肥大症の手術術式は下記の通りです。
①経尿道的前立腺切除術 (TURP)
②経尿道的前立腺核出術(電気メスを使用するもの;TUEB ホルミウムレーザーを使用するもの;HoLEP)
③経尿道的レーザー前立腺蒸散術(PVP、CVP)
④経尿道的前立腺水蒸気治療
⑤経尿道的前立腺吊り上げ術
性行為感染症
症状・診断・治療方法
性行為によって伝播される感染症を称して性感染症と呼びます。泌尿器科ではおもに男性の性感染症を治療します。
性感染症はコロナウイルス感染症の流行があっても、尚、増加傾向の感染症です。特に最近は梅毒の急増が社会問題となってきています。
また、昨今、インターネットにて性感染症自己診断キットが流通していますが、特にクラミジアや梅毒は検査にて必ず陽性がでる訳ではありませんので、何か心配な症状がある場合は自己で診断せず、必ず泌尿器科専門医を受診することをお勧めします。
男性の主な性感染症は以下に列記します。
(1)尿道炎
排尿時の痛みや違和感を伴います。以前は淋菌、クラミジアが原因となることがほとんどですが、最近はマイコプラズマ・ジェニタリウムによる尿道炎の増加が問題となっています。マイコプラズマ・ジェニタリウムは抗菌薬が効きにくいという特徴があり、治療に難渋することがあります。また、その他にもウレアプラズマ尿道炎やアデノウイルス尿道炎などがあり、尿道炎の診断・治療は年々複雑化しています。
性感染症にかかるリスクのある性行為後に排尿時の症状が出現した場合は、必ず泌尿器科専門医を受診しましょう。
(2)梅毒
急速に増加傾向の感染症です。
男性では性器に硬結(かたい出来物)や潰瘍が出現します。多くは痛みを伴いませんが痛みを伴うこともまれではありません。
現在のところ、梅毒の診断は血液検査による梅毒反応の上昇を確認するしか方法がありません。しかし感染後間もない早期梅毒では血液検査による梅毒反応が上昇しないことが多いです。ですから、梅毒の診断は視診が最も重要です。梅毒を疑う症状があれば、必ず泌尿器科専門医を受診しましょう。
梅毒は抗菌薬(ペニシリン系)を1ヶ月内服することにより完治する病気です。恐れず早めに受診をしましょう。
(3)性器ヘルペス
性器に水泡や潰瘍ができ、通常強い痛みを伴います。梅毒との鑑別が重要ですが、迅速抗原検査キットにて診断ができます。
治療は抗ウイルス薬を内服することにより1-2週間で完治します。
しかし、性器ヘルペスは再発が一番の問題となります。一旦ヘルペスウイルス性器に感染するとこれを除去することは不可能で、一生潜んでいることになります。体の免疫が落ちた時に再度発症することがあり、これを再発といい多い人では月に1回再発する場合もあります。再発の頻度が多い場合は、再発抑制療法を行います。
(4)尖圭コンジローマ
性器にカリフラワーのようなイボができる疾患です。痛みは伴いません。HPVウイルスによる感染が原因です。診断は視診のみで、検査はできません。
内服による治療はなく、クリームによる治療もしくは外科的切除が必要になります。
尖圭コンジローマも再発が問題となります。性器ヘルペスと違い、内服での治療もなく再発抑制治療もありませんので、非常にストレスのかかる性感染症といわれます。
尖圭コンジローマは男性の性感染症で唯一ワクチンにて予防が可能な疾患です。HPVワクチンを接種することにより、高い予防効果が示されています。(本邦ではまだ男性に対するHPVワクチン接種は公費補助がなく、自費治療になります。)
|
膀胱癌
症状・診断・治療方法
膀胱は下腹部にある臓器で、腎臓から流れてくる尿を貯め、充満すれば収縮し尿を排出する働きがあります。膀胱の壁は三層(粘膜、粘膜下層、筋層)から構成されており、この外側は脂肪組織に覆われています。膀胱癌とは、この粘膜上皮から発生する癌であり、進行するにつれ粘膜、筋層および周囲脂肪組織の順に浸潤していきます。一般的に膀胱癌は高齢の男性に多くみられる病気で、(男性が女性の約3倍と言われています)喫煙・特定の薬物や色素などへの接触も危険因子とされています。
症状
痛みなどの症状を伴わない血尿で発見されることがしばしばで、排尿困難や頻尿を認める場合もあります。
診断
尿検査や超音波検査に加え、膀胱の内視鏡(膀胱鏡)を行って診断します。その他、癌の進行程度(病期)を調べる検査として、CT、MRIおよび骨シンチなどがあります。
治療方法
【手術】
手術には、内視鏡手術(経尿道的膀胱腫瘍切除術)と膀胱全摘除術(開腹、腹腔鏡、ロボット支援手術)とがあります。まず、癌であるかどうか、腫瘍の深さをみるため内視鏡手術を行います。表在性癌(浅い癌)であれば、内視鏡手術のみで治療可能となりますが、浸潤癌(根が深い癌)では、さらに追加の治療(膀胱全摘除術、抗癌剤治療および放射線治療)が必要となります。手術は、男性では膀胱と前立腺とを、女性では膀胱と子宮、卵巣、膣との一部分をあわせて切除します。また、膀胱を切除してしまうと尿の通り道がなくなるため、新たな道を作成することが必要となります(尿路変向術といいます)。
【尿路変向術】
(1)尿管皮膚瘻左右の尿管をお腹の前面に導き固定し、出てくる尿を採尿袋で受けます。
(2)回腸導管小腸を遊離して、これに両側の尿管をつなぎ、小腸の一方端をお腹に誘導する方法であり、これも採尿袋が必要です。
(3)新膀胱小腸で膀胱に見立てた袋(新膀胱)を作り、これに両側の尿管および尿道とつなげる術式です。もっとも自然な尿の流れとなり、自力で排尿が可能でお腹に採尿袋をつける必要がありません。ただ、尿が漏れることや、排尿がうまくできなかったりすることもあります。
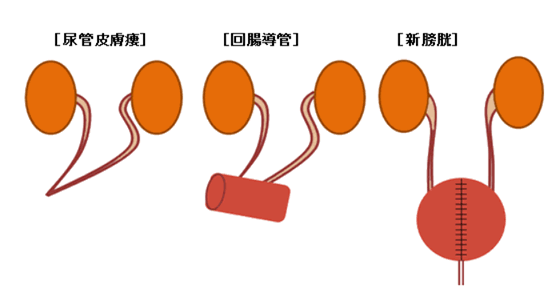
また、手術前に白金製剤を用いた抗癌剤治療をしたり、再発リスクの高い場合は術後治療として抗癌剤治療や免疫チェックポイント阻害薬による免疫治療を追加することもあります。
【薬物治療】
診断時に転移のある場合や手術が困難な場合は、抗癌剤を用いた薬物治療を行います。また1次治療である抗癌剤治療後には2次治療として免疫チェックポイント阻害薬を用いた免疫治療、その後の再発には3次治療としてエンホルツマブ ベドチンという抗悪性腫瘍剤による治療を行います。
副腎腫瘍
症状・診断・治療方法
副腎は腎臓の上方に存在する数cm臓器で、血圧を調整するホルモンをはじめ多種のホルモンを分泌しています。
副腎腫瘍
副腎の腫瘍はほとんどが良性ですが、特に大きなサイズのものでは癌(副腎癌)の可能性があります。分泌されるホルモンにより高血圧など多彩な症状を示しますが、検診等で偶然発見される副腎腫瘍も増加しています。これらのうち、ホルモン産生を伴わない非機能性腫瘍に関しては、小さなもの(3cm以下)であれば定期的なフォローでよい場合もあります。
・ホルモン産生腫瘍
(1)クッシング症候群(コルチゾールの過剰分泌)
(2)原発性アルドステロン症(アルドステロンの過剰分泌)
(3)褐色細胞腫(アドレナリンの過剰分泌)
治療
侵襲性の低い腹腔鏡下での手術を行っています。
尿路結石
症状・診断・治療方法
腎臓から尿道に至る尿の通り路に結石ができる病気を尿路結石症といいます。尿路結石の成因については80~90%が不明とされていますが,尿路疾患(尿路通過障害)が潜んでいたり,代謝性疾患(カルシウム,尿酸,アミノ酸代謝異常)が発見されることも稀ではありません 。
尿路結石は、男性は7人に1人、女性は15人に1人が一生に一度はなるといわれています。また、食生活の欧米化や温暖化による脱水傾向などの原因で年々尿路結石にかかる人の数は増加傾向です。
症状
尿管につまった尿管結石は、突然の脇腹や背中の激痛を引き起こします。
「夜中に激痛で救急車で運ばれた」「今までに感じたことがない痛みで動くことができなくかった」
など、初めて尿路結石による痛みを経験すると、なにか大変なことが身体に起こったと感じ、痛みとともに不安に襲われます。尿路結石による痛みは、人間が感じる最も強い痛みの一つとされています。
また症状が無くても尿路結石は尿路感染症の原因となり、長い間放置すると腎臓の機能が著しく低下することもあります。
治療
尿路結石の患者さんに、「結石を溶かすような薬はないのか」とよく聞かれます。残念ながら現在はそのような薬は存在しません。ですから、尿路結石の治療は結石を破砕する手術が必要になります。体外で発生させた衝撃波により、細かく砂状に結石を破砕し、尿とともに自然に体外に排出させる体外衝撃波結石破砕術(ESWL)やESWLでは治療困難な症例に対しては、軟性尿管鏡を用いたレーザー砕石術(fTUL)・細径腎盂鏡による経皮的腎尿管結石砕石術(miniPNL)およびf TUL併用PNL(TAP)などの最新治療も行っています。
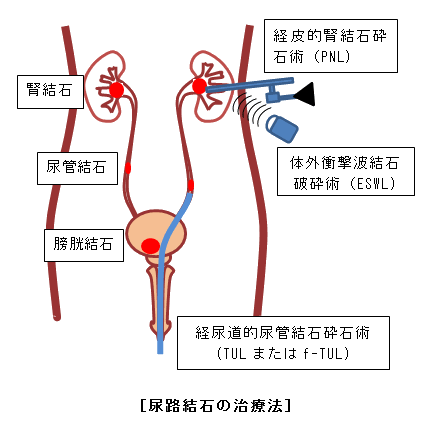
尿路性器感染症
症状・診断・治療方法
尿道・膀胱・腎臓など尿の通り道(尿路)のどこかに細菌(主に大腸菌)が尿道より入り込んで炎症を起こす病気です。炎症を起こす場所によって、膀胱炎・腎盂腎炎・精巣上体炎・前立腺炎などに分けられます。
診断
検尿で尿中の白血球(つまり尿中の膿)および細菌が確認できれば尿路感染症と診断します。また同時に尿中細菌を培養し、どのような種類の菌が原因か調べます。
症状
(1)膀胱炎:頻尿、排尿痛、残尿感、下腹部痛、尿の混濁などの症状を有し、ほとんどが女性に認められます。
(2)腎盂腎炎:発熱や腰の痛みを認めます。これも膀胱炎と同様に女性の割合が高頻度です。(3)前立腺炎:精巣上体炎:両疾患とも発熱を認め、前立腺炎は下腹部痛・排尿困難など、 また精巣上体炎では精巣の痛みを伴います。
治療
症状が軽微であれば、外来での抗菌薬投与ならびに水分を充分に摂取することで軽快します。しかしながら、高熱(38℃以上)が続く場合などは入院の上、点滴治療が必要となります。
|