尿の異常
・尿が濁っている
・おしっこがにおう
・排尿時に痛む
・尿検査で尿が濁っているといわれた
「小児尿路感染症と膀胱尿管逆流」
【尿路と尿路感染症】
尿路とはおしっこを作る腎臓、尿を体の中にためておく膀胱、その間を結び尿を腎臓から膀胱に運ぶ尿管、尿を膀胱から体の外に出す通り道である尿道からなっています。
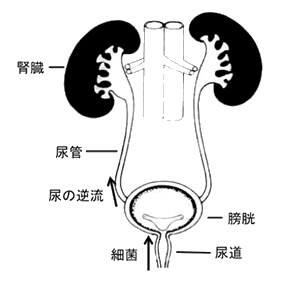
尿路感染症は細菌(ばい菌)が体外から尿道を通って、尿路に侵入し繁殖することによっておこります。菌の侵入が膀胱までにとどまれば熱の出ない無熱性尿路感染(大人でいう膀胱炎)といい、菌が腎臓まで達すると、38度以上の高い熱を伴う、有熱性尿路感染(大人でいう腎盂腎炎)となります。
ここで述べる尿路感染とは、主に有熱性尿路感染のことです。有熱性の尿路感染症は入院が必要なほど重症化してしまうことが珍しくありません。さらに、腎臓にとりついたばい菌はこどもの腎臓に傷をつけ(これを腎瘢痕といいます)、その機能を落として行ってしまいます。
【有熱性尿路感染症と尿路の先天異常】
有熱性尿路感染は一歳未満では男の子に、一歳以上では女の子の方に多いですが、いずれの場合にもその背景には尿路の先天異常のある場合が多く、その場合尿路感染症は再発しやすくなます。代表的な先天異常としては次のようなものがあります。
1)膀胱尿管逆流症
2)先天性の水腎症
再発する尿路感染により腎臓の機能が落ちていくのを防ぐためには、有熱性尿路感染症を繰り返すお子さんでは超音波検査と膀胱造影検査によりこのような異常の有無を確認しておくことが勧められます。膀胱造影検査を受けさせるのには少し覚悟が入りますが、感染を繰り返して腎臓が傷ついていくまで検査を受けないのもやはり避けたいところです。
また、尿路感染をまだ起こしたことがない子供でも、超音波検査で腎臓にはれが認められる場合には逆流がその原因となっている場合があり、検査をおすすめする場合があります。
【膀胱尿管逆流とは】
尿管と膀胱のつなぎ目は、いったん腎臓から膀胱におりてきた尿がまた腎臓に戻らないようにする弁の機能を持っており、ばい菌が膀胱の中にいても普通は腎臓まで達することはありません。膀胱尿管逆流症とは、この弁機能が未成熟なために膀胱の中の尿が腎臓の方に逆流することで、腎盂腎炎を発症しやすく腎臓にダメージを与えていきます。
【二次性の逆流】
また、元来つなぎめの異常がなくても、異常な排尿習慣や膀胱の神経疾患のために膀胱の中の圧が異常に上昇しておこる逆流もあり二次性の逆流と呼ばれます。その場合は排尿そのものの管理が重要です。
【診断方法】
排尿時膀胱尿道造影
膀胱の中に造影剤を入れて行うレントゲン検査です。この検査により逆流の有無とその程度がわかります。
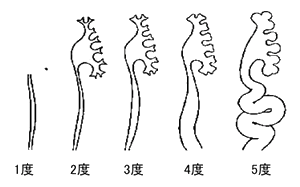
【RI(アイソトープ)検査 】
腎臓のシンチグラフィー(略して腎シンチ)ともいいます。造影検査で逆流があることがわかった場合に、左右の腎臓の大きさと、腎臓についた傷(腎瘢痕)の有無の診断のために行います。
【治療方針について】
治療方針はこどもの年齢、逆流の程度、尿路感染症の頻度と重症度、腎臓へのダメージの程度とその進行、保存的治療の経過、などを総合して考えていきます。
1)保存的治療法
多くの場合こどもが成長するとともに尿管と膀胱のつなぎ目は成熟し、逆流の程度は軽減していきます。そこで、造影検査を1、2年おきに繰り返して経過を見ていくことになります。逆流がある間は、有熱性尿路感染の発症を防ぐために抗生物質を長期間にわたって一日一回少量服用します。それでもその予防効果を乗り越えて尿路感染を起こしてしまう場合には手術療法が勧められます。
2)手術療法
下腹部に約4-6cmの横切開をおき、尿管と膀胱をつなぎ直す手術です。
対象は、1)逆流の程度が強いとき、2)予防的抗生剤を投与しても重症の尿路感染症を発症するとき、3)腎臓へのダメージが大きいときです。保存的治療法で、中程度の逆流が最後まで残存した時にも考慮する場合があります。最近はおなかを切らずにおこなう腹腔鏡下手術も選択されることがあります。
3)内視鏡手術
尿管と膀胱のつなぎ目に補強剤を内視鏡下に注射する方法です。つなぎ直す手術よりも根治性に劣り、麻酔は必要ですが、傷が残らずすぐに退院できますので開腹手術よりもはるかに簡単です。
検診で異常を指摘された
・尿が赤くなった
・尿検査で血が混じっているといわれた
・尿検査でタンパクが出ているといわれた
「小児の血尿とタンパク尿」
【血尿】
血尿をきっかけとして膀胱や腎臓の癌が 発見されることが中高齢者ではよくありますが、小児ではまれです。血尿の原因としては尿路の細菌感染がありえますので、詳しい尿検査がまず必要です。感染がない場合、小児期の血尿の原因としては泌尿器科的なもの(腎臓で作られた尿が体外に運ばれていく途中で血液が混ざること)よりも、内科的なもの(腎臓で作られる尿そのものに 血液 がまざっていること)であることの方が多いです。
泌尿器科的な疾患として、 腎や膀胱の先天異常(水腎症や膀胱尿管逆流症)の発生頻度は比較的高く、それが原因となって感染を合併することがあります。成人のように悪性腫瘍や結石が尿路に発生することはまれですが皆無ではありません。ウイルムス腫瘍や横紋筋肉腫など尿路に発生する小児がんも存在します。これらの病気は腹部超音波検査などによりスクリーニングが可能です。また、尿中のカルシウムの濃度が高い人(高カルシウム尿症)に顕微鏡的血尿が認められることがあり、尿路結石のリスクと関連づけられています。
内科的な疾患としては、IgA 腎症などの糸球体腎炎(いわゆる腎臓病)が重要です。
これらは将来腎臓の機能をおびやかす病気ですが、経過中に血尿が増悪したりタンパク尿の出現がみられるので、定期的な尿検査が早期発見には重要です。
【タンパク尿】
血尿がなくタンパク尿だけが認められた場合には内科的にはネフローゼ症候群などの腎臓病がうたがわれますが、尿路の先天異常によってどちらかまたは両方の腎臓に障害がおこっている場合がありますので、やはり超音波などによる精査が必要です。
それらが否定されれば、病的意義のない血尿やタンパク尿と考えます。
|
尿失禁
・尿の回数が多い
・尿の回数が少ない
・突然尿意をもよおし、トイレが間に合わなくて漏れてしまう
・昼間におしっこを何回もちびる
「排尿習慣の異常と昼間の尿失禁」
昼間におもらししているこどもの中には、身体のつくりそのものに異常のあるお子さんもおられますが、実際はきわめてまれです。大部分のお子さんは異常な排尿習慣を身につけて育ってしまったために、排尿の各要素が協調してはたらくことができなくなっているのです。幸いそのようなお子さんはちゃんとしたトレーニングをすることで、正常なパタ
ーンを身につけることができます。
【異常な排尿とは?】
排尿するときに尿道を中途半端にしか開いておらず、絶えず排尿を我慢しながら尿を出していると、膀胱の筋肉が過度の力をかけないと排尿できないので、膀胱の緊張を招きます。これは尿もれなどの症状の原因となります。膀胱の発育が遅れてひっきりなしに排尿したり、ぎゃくに全ての尿が排尿できず(残尿)、膀胱内での感染(無熱性)を引き起こす
こともあります。ひどい場合には、膀胱内の圧の上昇から腎臓への尿の逆流や感染(有熱性)を引き起こす事すらあります。
【どのようして子供はそういう異常なパターンを身につけるのでしょうか?】
異常な排尿習慣を形成する経緯はよくわからない場合も多いですが、排尿を意識的にコントロールするようになる発達過程の遅れと考えられます。
重要な要素として性格があげられ、いそがしがりやさんや多動児の場合が多いです。排尿をきちんとするためには、落ち着いてリラックスすることがなによりも大切なのですが、そのような子供は一刻も早く遊びに戻りたいあまり、きちんとした排尿の動作をさぼりがちです。
さらに社会や家庭内での精神的なプレッシャーも正常な排尿発育の大きな敵です。子供達が家庭内でのいざこざや、親の離婚、アルコール中毒などに過敏に反応して排尿異常の症状が悪化することがあるのは有名です。いじめや、転校もそのきっかけになることがありますが、明らかな原因なしにそうなった子供も多いです。
【感染と便秘】
感染と便秘は、このような状態に合併しやすく、症状を悪化させる重要な要素です。異常な排尿習慣があると膀胱内にばい菌が入りやすくなり(尿路感染、膀胱炎)、その刺激がまた異常な排尿習慣を助長します。また、このようなこどもでは便秘を合併していることが珍しくなく、その場合には宿便による慢性的な刺激が、排尿の神経に悪影響を及ぼした
り、便失禁の原因になります。
【診断方法】
専門の医師にくわしくお話をきかせてください。現在の排尿状態に至った経緯と、排尿パターンを聞かせていただければ、それだけで病状を把握できる場合がほとんどで、最近では自己記入したアンケートもあります。
1)検尿と超音波検査: 痛みも危険性もなしにでき、多くの情報が得られる検査です。検尿で感染の有無がわかります。超音波検査により、まれな先天異常の有無から、膀胱壁の状態、残尿の有無まで、多くの情報を得ることができます。
2)排尿日誌:2、3日間にわたり全ての排尿の量と時間を紙に記録してもらいます。これにより本人や親御さんも意識していないような排尿の異常がはっきりします。
3)おなかのレントゲン写真:便のたまり具合や二分脊椎という異常の有無を把握します。
4)尿流測定: 上手に排尿ができているかどうかを客観的に記録します。
5)膀胱内圧測定と膀胱尿道造影: 最も正確な精密検査です。膀胱内圧測定は細い管を尿道から膀胱に通し、膀胱に水を注入していって、膀胱の大きさ、内部の圧(緊張)、排尿するときの圧、括約筋の緊張をみる検査です。水の代わりに造影剤を入れてレントゲン撮影をするのが膀胱尿道造影で、膀胱の形、尿道の形、排尿時の尿道の開き具合を同時
に観察できます。この二つの検査は同時に行えば、尿道に一回だけ管を通すだけで全ての検査を終えることができます。ただ実際には、ほとんどのお子さんはこのような精密検査を行わなくても適切な対策により治癒することが可能です。
【治療方法】
1)行動療法(定時排尿)
排尿中にリラックスして膀胱に負荷を与えない習慣を身につけることを目的として、2時間おきに時間を決めて排尿するです。
2)膀胱の緊張をとる薬物療法
膀胱の緊張をとる薬副作用として、口の乾き、便秘などがあります。
3)感染と便秘のコントロール
慢性の感染状態は、抗生物質を少な目の量で服用することで治療と予防が可能です。便秘がある場合には、下剤や浣腸を積極的に使用して宿便のたまった状態を是正します。
おねしょ(夜尿症)
5歳をすぎて睡眠中に無意識に排尿している
「子どものおねしょ(夜尿症)」
夜尿症は、「5歳を過ぎて週に2回以上の頻度で、少なくとも3か月以上の期間において夜間睡眠中の尿失禁を認めることです。7歳児における夜尿症の頻度は10%程度とされ、その後は年間15%ずつ自然に治り、成人までにほぼ全例が治ります。男児に比較的多いです。
原因として、夜寝ている間の尿量が膀胱(ぼうこう)に貯められる尿量より多いと、夜尿症につながります。夜尿症は、(1)睡眠中に膀胱がいっぱいになっても、尿意で目をさますことができないという覚醒障害、(2)膀胱の働きが未熟である(膀胱の容量が小さい、ある程度膀胱に尿が溜まると膀胱が勝手に収縮してしまう)、(3)夜間尿量が多い(夜間多尿)、
などいくつかの原因が複合して発生します。
診断に重要なのは問診と、排尿の記録(排尿日誌)です。
トイレが近い、トイレまで間に合わなくて尿をもらすという昼間の症状があれば、尿を貯める膀胱の働きが明らかに未熟である可能性が高いです(→「小児の排尿異常と尿失禁」へ)
夜間のおむつの重さの変化(使用後のおむつの重さから使用前のおむつの重さを差し引いた量)と起床時の排尿量を加えたものが夜間尿量で、これが多ければ、夜間多尿型の夜尿症が疑われます。
小学校に入っても夜尿症が治らず本人のストレスの原因となる場合には、小児科あるいは泌尿器科を受診することをお勧めします。夜決まった時間に起こすのは良くありませんが、適切なタイミングで起きれるように夜尿が起こるとブザーが鳴って知らせる夜尿アラームを治療に用いることがあります。膀胱型の夜尿症では、定時排尿などの訓練や膀胱容
量を増加させる作用のある薬剤(抗コリン薬)など昼間の排尿異常や尿失禁と同じような治療を行います。夜間多尿型では塩分や水分のコントロールが大切ですが、最近は夜間尿量を減少させる効果のある薬剤を就眠直前に使用することも可能です(抗利尿ホルモン療法)。
|